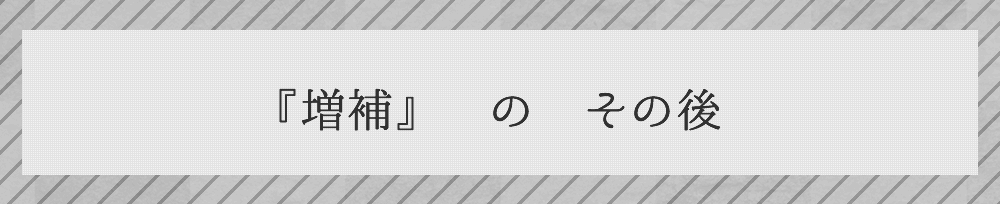
レジームシフト理論の発生
漁業資源管理に影響を与える新たな視点
新たな魚種交代と卓越年級群の発生
レジームシフトとは?
「大気・海洋・海洋生態系からなる地球の動態の基本構造が数十年間隔で転換すること」広辞苑
神奈川県横浜漁協柴支所(小柴)のシャコとレジームシフトとの出会い。
小柴では、2010年までの約5年間、資源回復のために小型底引き網漁の操業停止を決定した。10年ほど前から激減していたシャコの漁獲量が、遂に絶望的な状態にまで落ち込んでしまったからだ。しかし2010年3月末に到っても、資源の回復は満足の行くものではなく、操業再開延期の声もある中で、5月16日、淡い期待と共に操業が再開された。
一方、全国のシャコの産地状況を調べてみると、10年ほど前から共通して不漁又は大不漁の状況に移行していたことが判った。東京湾、三河湾、知多半島、瀬戸内の燧灘、大分県の周防灘、石巻、青森県の陸奥湾までもが激減していた。このように全国的に獲れなくなっている状況を見ると、環境破壊と乱獲、温暖化、行政による漁業規制の失敗等々の他に、何か別の共通の原因があるのではないだろうかと感じ始めていた。アナゴもコハダもクルマエビも同じような現象を見せているようだ。
そんな時に、1983年に東北大学の川崎健教授が報告し、国際的に認知されていったレジームシフト理論と200カイリ排他的経済水域の発生とそれに伴う日本の漁業規制のあり方の問題に出くわしたのだった。
以下、川崎健教授の理論とその考え方を解説している本多良一氏の著書を要約しながら、レジームシフト理論の漁業政策に与える影響、さらには地球全体の環境問題にも敷衍して行くという画期的な理論の真髄に触れてゆくことにする。
本多良一著
『イワシはどこへ消えたのか』
「イワシはどこへ消えたのか」
「1983年、当時東北大学農学部教授(現同大名誉教授)だった川崎健氏は、国連食料農業機関(FAO)主催の専門会議で、3地点の漁獲量を重ね合わせた図を示しながらこう報告した。
「『太平洋で互いに遠く離れて分布している極東マイワシ(日本のイワシ)、カリフォルニァ・マイワシ、チリ・マイワシの三つの資源の大変動は、同調している。このような共通の変動の原因を、太平洋規模の海洋変動とそれに関連する気候変動を考慮に入れずに説明することは困難である』しかし、当時の国際学会での反応は冷ややかなものだった。そして3年後、これらの地域で獲れるマイワシとカタクチイワシ・アンチョビの漁獲量が、一方が増えると一方が減るという逆相関関係があることを報告した。そしてこの時に反応した米国、メキシコなどの研究者たちとレジーム・チェンジ・ワークショップを立ち上げ、これが後のレジームシフトという概念に発展していった。その後、日本人研究者たちの研究成果と共に、地球物理学者や海洋物理学者たちも注目し始めた。そして地球或いは大洋スケールの気候変動と、マイワシなどの水産資源の長期変動の研究が融合し、レジームシフトという概念が定着していった。1996年、『川崎は帰ってきた』と当時批判的であった学者たちによっても認められ、新たな脚光を浴びて『レジームシフト』として学会の主流を占める理論となった」
レジームシフトとは
「大気と海洋の変動は相互に密接に関連している。気温や海水温度など気候を構成する要素は、ある程度長期間にわたって持続したあとで、急激に変化する。そして、その影響を受けて海洋生態系も変わる。海洋生態系を構成する要素の一つが水産資源、つまり魚だ。その変化の代表的な例がイワシ、サンマなどに代表される魚種交代という現象だ。人口孵化・放流が行われている秋サケなどのほか、天然アワビなどの貝類や海藻類も影響を受ける」という理論を言う。
TAC(タック)へのレジームシフト理論の影響と展開
国連海洋法条約に基づき、各国は自国の200カイリ排他的経済水域で魚種ごとの漁獲可能量(TAC)の設定を義務づけられることになった。しかしレジームシフト理論の導入によって、このTAC管理の基礎となっている最大持続生産量(MSY)理論が否定され、水産資源の新たな管理方法が求められるようになった。
◎TAC(漁獲可能量)は、ABC(生物学的漁獲可能量)をもとにしたMSY(最大持続生産量)理論によって前年の漁獲量の集計・推定のもとに設定されている。
◎MSY(最大持続生産量)とは、魚は獲れば減る。獲らなければ増える。しかし、無限に増えるかといえば、餌や生活環境に限界があるのでそうはならない。そこで魚を獲る場合は、自然の再生力を考慮し、資源を減らさない範囲で漁獲量を最大にしようという理論を言う。
MSYとレジームシスト理論の対立…新たな視点の発生
MSY理論では、環境の変化を短期的にランダムに生ずるものとし、イワシ資源の減少の原因は乱獲しかないが、レジームシストの理論では環境の変化(10数年スケールで、一定の法則を持って)を重視する。その環境の変化が漁業の世界では魚種交代という形で現れる。それは単に魚のことだけではなく。大気、海洋、海洋生態系という地球全体がひとつのシステムとして変化すると考える。
レジームシフト理論の影響
1)魚種交代の発生
気候の変動→海水温の変化、各魚種の適水温の変化→海中の撹乱→プランクトンの大発生→→魚種交代
異なる水温への変化と適応魚種の発生
二重の魚種交代のサイクル(川崎健)
(1)マイワシ→カタクチイワシ→マイワシ
(2)マイワシ→サンマ→マアジ→マサバ→マイワシ
単純に適水温だけを考慮すると
(3)マイワシ→カタクチイワシ・マアジ・スルメイカ→マサバ→マイワシという一つのサイクルを考えることが出来る。
2)卓越年級群の発生
特定の年に生まれた固体(年級群)が爆発的に増加することによって引き起こされる、急増した年級群が卓越年級群と呼ばれる。ある年に生まれた年級が卓越年級群となるかどうかは、親になる魚の数、つまり親魚量に加えて、どの程度の割合の卵が稚魚まで育つかどうか、つまり卵から稚魚までの生残率、すなわち初期の生残率によって決まる。
稚魚まで育てばその後の生残率は安定しているからだ。いいかえると幼魚が育ちやすい環境かどうかで、卓越年級群が生まれるかどうかが決まる。それを決めるのは環境だ。環境は「大気―海洋―海洋生態系」という地球の基本的な構造(レジーム)によって決定される。
◎魚種交代の阻害要因→その除外は有効な漁業資源管理規制対策となる。
(1)減少期に突入した魚に対するさらなる漁獲圧力(漁船の隻数・操業回数・その際の網数といった漁獲する強さのこと)を増すこと。
(2)魚種交代時に、漁業法のしばりによって、増大する漁獲対象魚への転換の禁止と、そのために発生する減少魚へのさらなる漁獲圧力の増加。
(3)漁船の耐用年数と特定魚種の漁獲ピーク期間のずれによる投資とレジームシフトとのずれ
(4)卓越年級群の発生時の漁獲圧力の増加による乱獲
レジームシフトによる新たな視点の発生
漁業は誰のものか?
川崎健氏は「環境との両立、調和という考えではいけません。両立を考えると、資源をつぶし、漁業はダメになります。まず、人類共有の財産である海に資源、地球環境を守ることを考えなければならない。海の資源を単なる人間の食欲の対象にしてはいけません。漁業問題は地球環境問題なのです」と言う。
本多良一氏は「水産資源は国民のものであり、人類共通の財産であり、それを地球環境のひとつと位置づけるならば、漁業、水産資源管理は、漁業者、水産関係者のためだけのものであってはならない。漁業や水産資源管理をどう管理していくのかという政策立案にあたっては、漁業者や関連業界の声を聞くだけでは済まないのだ。
漁業、水産資源管理政策のなかに『環境』というキーワードが入ることになるだろう。外部にいた人々が新たな政策立案にかかわることになるから。自分たちの都合を優先させて考えることができなくなるかもしれない。しかし、水産資源が国民のものであり、さらに人類共通の財産という位置づけが出来れば、資源の維持や保存に対し、これまでより多くの国民の関心が寄せられるだろう。また、より多くの国民が漁業者の声に耳を傾けるようになるだろう。それは結果として国の政策順位を上げることになるはずだ。そのためには、もちろん漁業者自身が水産資源を国民の財産、人類の共有物として考え、それを守り、育てていく姿勢が必要になってくる。漁業、水産資源管理の分野に新たな視点が加われば、それにふさわしい新たな政策展開の可能性もきっと生まれてくるだろう」と言う。
衰退する東京湾内湾及び日本漁業の現状とその原因を調べている内に、レジームシフトと言う川崎教授による画期的な新しい理論の登場を知った。漁業再生のための各種漁業規制の有り様に、新たな視点が加えられることになったのだ。水産資源を国民の財産、人類の共有物と考えるという壮大な視点は、余りにも漠然とした抽象的な言いようで違和感があり、漁業者、水産関係者にもまだまだ理解されるのは難しいと思うのだが、これからは水産関係者全体で考慮に入れてゆかなければならないのだろう。
しかし「近年の日本漁業の衰退振りの主原因を環境破壊と乱獲、さらには温暖化の影響によるものとし、日本の漁業の再生とは、漁業者と漁業資源の食料資源としての再生であると言うだけではなく、空気や水に見られる、地球環境としての再生、維持、保全であるという大きな視点から、国家政策の優先順位とされていかなければならない」と言う。しかしこの画期的な理論を知っている人は、僕の回りの水産資源関係者の中では、まだほとんど皆無の状態でさえある。
平成22年11月15日
↑『増補』のその後の目次へ
